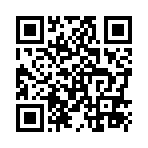2015年01月06日
「春の七草」の覚え方 七草がゆ
明日(1月7日)には 七草がゆを作る方も多いのではないでしょうか。

去年の七草がゆ
由来などは、去年のブログに載せてありますので、
よろしかったらご覧ください。。
http://vegefrumamma.ti-da.net/e3639128.html
古い文献に
七草粥の作り方として
「前日の夜に、七草をまな板に乗せて、囃し歌を歌いながら包丁で叩き、
当日の朝に粥に入れる。」
との記載がありました。
囃し歌は鳥追い歌に由来するもので
七種がゆの行事と、豊作を祈る行事が結び付いたものと考えられている。
とのことです。
前日の夜に まな板の上で叩き、当日の朝入れていたことは
私も知りませんでした。
さて、その春の七草は
芹、なづな、御行、はくべら、仏座、すずな、すずしろ
●芹(せり)
水辺の山菜。芳香により食欲増進の効果。
●薺(なずな)
別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材。
●御形(おぎょう・ごぎょう)
別称は母子草(ハハコグサ)で、草餅に使われていた。
風邪予防や解熱効果が期待された。
●繫縷(はこべら)
目の疲れ、腰痛の時の薬としても使われていた。ビタミンAが豊富
●仏の座(ほとけのざ)
別称タビラコ。タンポポに似ていて、豊富に食物繊維を含む
●菘(すずな)
蕪(かぶ)のこと。ビタミンCが豊富。
●蘿蔔(すずしろ)
大根(だいこん)のこと。消化を助け、風邪の予防に。
覚え方としては 5 7 5 7 7 のリズムで
せりなずな
ごぎょうはこべら
ほとけのざ
すずなすずしろ
春の七草
と覚えるのおすすめですが
こんな、かんたんで面白い覚え方があります。
「鈴木さん、箱の中にホットケーキ5枚と鈴千個」
すずきさん、はこのなかにほっとけーきごまいとすずせんこ
ほかにもいろいろあるようですが
美味しそうな覚え方を考えてみるのも面白いかもしれませんね。
そう言えば、鈴木さん、お元気かなぁ~? (#^.^#)
いつも応援クリックしていただきありがとうございます。
にほんブログ村
にほんブログ村
先日、お名前の入ったカリフラワーを、糸満ファーマーズマーケットで購入しました!
ことしも、ご活躍を祈念しています。
お互い、頑張りましょう!
わぁ~うれしい。お元気そうで、安心しました。
私の野菜をお求めくださったんですね。ありがとうございます。最近は、野菜を届けることもできず、ごめんなさい。
今年もよろしくお願いいたします♪
 at 2015年01月07日 21:37
at 2015年01月07日 21:37